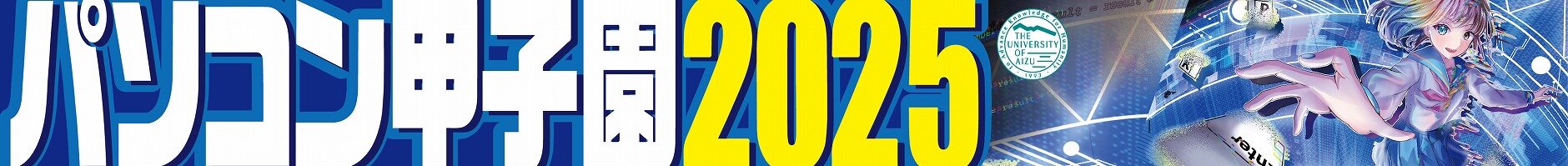

モバイル部門
競技内容
概要
モバイル部門競技では、Android搭載のスマートフォンを対象に、テーマに基づいた"夢のある"アプリケーション(以下アプリとする)を企画・開発し、その総合的なプロデュース力を競い合います。
競技要項
競技要項は下記のとおりです。応募を検討している方は、必ずご確認ください。
動画
下記の紹介動画も参照ください。
今大会テーマ
「地域創成~アプリでささえるまち・ひと・しごと~」
皆さんは「まちづくり」と聞いて、どのようなことを思い浮かべるでしょうか? 最近は、YouTubeなど、新しいメディアによって、国だけではなく地域の課題や「まちづくり」を見ることが出来るようになりました。実際、デジタル技術の進化によって、私たちの暮らしやコミュニティのあり方が大きく変わりつつあります。その中で、スマートフォンやインターネット、アプリケーションを活用することで、新しい形の「地域創成」が可能になっています。
例えば、買い物支援、交通情報、地域イベントの共有、防災対策など、私たちの身近な生活を便利にし、より良い地域社会を作るためのデジタルツールは数多く存在します。こうしたテクノロジーを駆使し、「アプリを通じて、まち・ひと・しごとを支える」ことが、これからの地域創成の重要なテーマとなっています。
今大会では、「地域創成」に焦点を当て、デジタル技術を活用したアプリケーションの開発を募集します。皆さんが日々感じる地域の課題や、将来のまちづくりに対するビジョンを形にし、住みよい社会の実現に貢献するアプリを考案してください。また、単に技術的な開発を行うだけではなく、アプリを通して地域社会に役立つ新しいアイデアを創出することや、地域住民が楽しみながら関われる仕組みを考えること、持続可能で発展性のあるデジタルサービスを生み出すことも目指しています。特に、「夢のある、希望のある」企画を積極的に採用し、未来の地域づくりに向けたワクワクするようなアイデアを募集します。
あなたのアイデアが、未来の地域を変えるかもしれません。デジタルの力を活用して、私たちの暮らしをもっと便利に、もっと楽しくするアプリを考え、一緒に新しい地域創成の形を探求しましょう。
テーマに合致し、『夢や希望を感じやすい』と思われるアプリとは?
- 新しいコミュニティの形の提案を支えるアプリ(SNSや回覧板+αのαの部分が重要)
- 地域に根差した/特化した問題解決 (「楽しみながら地域を知る」など)
- 具体的な解決につながるアプリ (空き家、スマート交通、見守りなど)
テーマに合致しているが、『夢や希望を感じにくい』アプリとは?
- 社会的意義は大きいが、参加が難しいアプリ (防災、ごみ収集、健康管理など)
- 自分たちの問題意識が地域とかけ離れている(勤怠管理、タスク管理、SDGsの項目そのままなど)
- 「なんでもできるアプリ」になってしまっている(トータルソリューションは不要)
テーマに合致していない、あるいは外れる可能性の高いアプリとは?
- 地域創成や人とのつながりが薄いアプリ (単純なゲーム、クイズ、試験対策アプリなど)
- 「まち、ひと、しごと」を支えていないアプリ (一般的なチャット、日記、写真共有)
- 地域との関連性が薄いアプリ (投資、資産形成、占い、性格診断など)
- 不要なインセンティブ (育成アプリ、コンテンツ収集など)
評価されやすくするための工夫ポイント
- ストーリーの明確化 (なぜこの地域?どう変えていきたい?)
- 参加型と参加の戦略 (誰に、どのような付加価値を与えたい?)
- 成長や達成の可視化 (明確なスコアリング、達成感の強調)
競技ルール

同一学校の3名以内の生徒でチームを構成し、企画書及びアプリを制作します。
※チームの構成人数は最大3名とし、1名からでも参加できます。
※競技要項の「7 応募上の注意(2)」もあわせて確認してください。
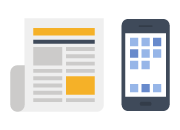
予選においては、テーマに基づき作成されたアプリの企画書を審査し、本選出場チームを決定します。本選出場チームはアプリの制作と本選会場での発表を行います。
※予選ではアプリの制作・提出の必要はありません。
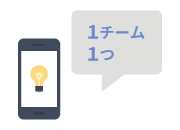
1チームにつき、応募可能な作品(企画書・アプリ)は1つのみとします。

応募作品はAndroid端末に対応したアプリとします(Webアプリも可)。
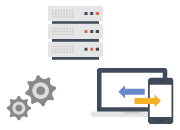
応募いただく作品には、以下のような構成が考えられます。
- ソフトウェアのみで構成されたアプリ
- ハードウェアと連携したアプリ
- 人の動きと連携したアプリ
- インターネットの情報と連携したアプリ
予選について
| 予選の方法 | パソコン甲子園事務局による審査会(応募者の出席を要しない)を実施し、応募のあった企画書の審査を行い、本選に進出する8チームを選出します。 なお、できるだけ多くの学校の本選出場が可能とように同一校からの選出は2チームまでとします。 |
|---|---|
| 予選の審査基準 |
以下の4つの観点を総合的に審査します。
|
| 予選の結果通知 |
2025年7月24日(木)に本選出場チームに対して本選出場通知を発送するとともに、出場チーム名、学校名及びチーム番号をパソコン甲子園公式ウェブサイトで発表します。 |
| その他 | 予選にかかる経費については、参加者の負担とします。 |
本選について
| 本選開催日 | 2025年11月8日(土)、9日(日) |
|---|---|
| 作品の制作及び提出について |
本選出場チームは予選において作成した企画書をもとに作品を制作し、2025年10月3日(金)までに提出します。その後、パソコン甲子園事務局による事前チェックを経て、本選で発表する作品を完成させます。
※本選出場チームの決定後、作品の提出まではおよそ2か月となります。 |
| スマートフォンの貸与 | アプリの制作にあたり、パソコン甲子園事務局より各チームそれぞれに1台ずつスマートフォンを貸与する予定です。 なお、それぞれのチームが用意したスマートフォンにより制作を行っても構いません。 |
| 制限事項 |
|
| 本選の方法 |
|
| 本選の審査基準 | 各チームの作品、プレゼンテーション及びデモンストレーション・セッションの内容を、以下の4つの観点から審査します。その上で、審査員は"夢のある"アプリを企画・開発する総合的なプロデュース力があるかどうかに重点を置いて協議し、入賞チームを決定します。 なお、来場者から最も優れていると思う作品を選んで投票してもらい、その結果は審査において考慮します。 <審査項目>
|
スケジュール
| 企画書受付期間 | 5月7日(水)~7月1日(火) |
|---|---|
| 本選出場チーム発表 | 7月24日(木) |
| 本選出場チーム作品制作期間 | 7月24日(木)~10月3日(金) |
| 事前チェック提出締切 | 10月3日(金) |
| 本選 | 11月8日(土)・9日(日) |
応募方法
- 以下1~2の提出書類を用意し、学校長の許可を得た上で、担当教職員が「応募フォーム」よりお申し込みください。
- 本選時の引率者となる担当教職員と参加者の連名により申し込んでください。同一の担当職員が複数のチームに含まれてもかまいません。
- 同じ生徒が複数のチームに所属することは認めません。
- 一校あたりの参加申込チーム数及び応募数に制限はありませんが、同一校から同一部門の本選への出場は2チームまでとさせていただきます。
| 企画書受付期間 | 2025年5月7日(水)~7月1日(火)※必着 |
|---|
※申込状況はパソコン甲子園のWebサイト上の「受付状況」にアップしますので、必ず確認してください。10日以上経過しても応募の情報が反映されていない場合は、パソコン甲子園事務局までご連絡ください。
1. 企画書
企画書のフォーマットは必ず所定の様式を使用してください。
※企画書に別途、作成した補足資料を添付することも可能とします。
※企画書の書き方やAndroidアプリについて詳しく知りたい人は、『Android Seminar for パソコン甲子園』をご覧ください。モバイル部門参加に役立つ情報を入手することができます。
※どのようなことを企画書に書けばよいかについては「企画書作成の手引き」をご参考ください。
応募上の注意事項
- 応募作品は、応募者本人たちが作成したものに限ります。なお、応募開始前、及び応募開始から本選開催終了まで(2025年11月10日(月)以前)に、他のコンテストへの重複応募は認めませんので注意してください。
- 作品の制作は、原則チームを構成する3名以内のメンバーのみで行うこととし、特に提出するソフトウェア用ソースコードの作成は、チームのメンバーのみが行ってください。 ソフトウェアのコンポーネントの一部を担当する等、補助的に携わった協力者がいる場合、もしくは応募者が制作していない素材等が作品に含まれる場合は、協力者の人数及び協力内容と、どのような素材等を使用したのか出自を明記し、作品に添付した上で応募することを認めます(企画の段階では企画書に記載し、作品の制作時は事前チェック提出時にA4サイズの用紙に上記の情報について明記し、添付してください)。なお、協力者は参加者と同じ学校の生徒(高校生及び高等専門学校生の3年生まで)に限ります。 協力者、素材等の内容を確認するため、パソコン甲子園事務局から応募者に連絡する場合があります。これらの情報について事前に連絡がなく、本選等において判明した場合は、審査において大きく減点します。
- 一旦応募いただいた企画書は、予選終了まで修正はできません。また、応募いただいた企画書はパソコン甲子園公式ウェブサイト上で公開することがあります。
- 作品のすべて又はその一部について応募者が著作権を有しない場合は、権利者から必ず使用許諾等を受けたうえで使用してください。第三者から権利侵害、損害賠償などの主張がなされた場合は、主催者は一切の責任を負いません。
- 応募のあった作品に係るすべての著作権は応募者に帰属します。ただし、応募者及び他の権利者は、主催者又は主催者が認めた者が作品の一部または全部を複製、上映、上演、放送、展示及び出版での利用を無条件で許諾するものとします。また、本選で発表されるアプリについては、パソコン甲子園公式ウェブサイト上にて無料でダウンロードできるかたちで公開、提供することがあります。
- 応募のあった企画書及びアプリは返却しませんので必ずバックアップをとってから応募してください。
- 応募に必要な経費については応募者の負担とします。
学習サイト
Android Seminar for パソコン甲子園
企画書のつくり方や、Androidについて詳しく知りたい人は、下記リンクにアクセスすると、
モバイル部門参加に役立つ情報を入手することができます。
避けた方が良い企画書の例や環境開発の構築についても掲載しています。ご参考ください。
協賛企業様提供の学習サイト
モバイル部門参加者全員に、2025大会にご協賛いただいている株式会社paiza様より、オンライン学習サービス「paizaラーニング」を無料でご利用いただける「フリーパス」をご提供いただいております。
モバイル部門参加者の皆さまには、事務局より全動画視聴可能となるクーポンコードをお送りします。
※paizaラーニング 学校フリーパスについての詳細は、こちらをご参照ください。
相談窓口
モバイル部門担当教員・会津大学生・事務局で構成されたモバイルチームが、アプリ開発における疑問や問題解決のアドバイスをします。下記フォームよりご相談ください。
※質問の内容によっては、お時間をいただくことがあります。また、不公平となるようなことはお答えできません。
参考:実際にリリースされたアプリ
アプリ制作の参考として、実際に Google Play Store / App Store にて公開されている、2023年のグランプリ作品を紹介します。(制作した作品を必ず公開する必要があるわけではありません)
| アプリの名称 | 「サステナボード」 ※パソコン甲子園2023 モバイル部門 グランプリ受賞 |
|---|---|
| 学校名・チーム名 | 学校名:宮崎県立佐土原高等学校 チーム名:「Unknown Prototype」 |
| アプリの概要 | 節約とSDGsの達成に貢献できる機能を詰め込み、簡単に使える仕組みにした家計簿アプリ。 お金の使いすぎ防止や2030年SDGs達成を手助けすることを目的としており、 様々な場面でSDGsを意識した消費行動を手助けする。 |
| アプリのダウンロード | ■Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.shsit.sustinaboard 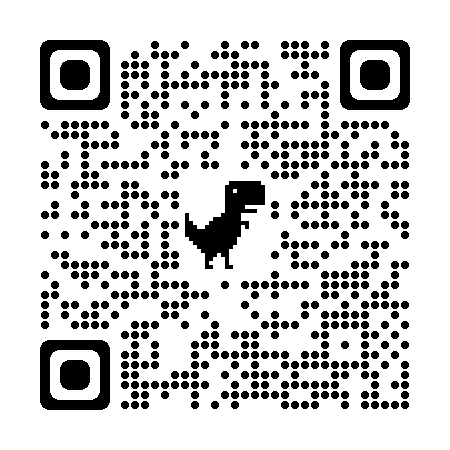 ■Apple https://itunes.apple.com/jp/app/id6474093228?mt=8 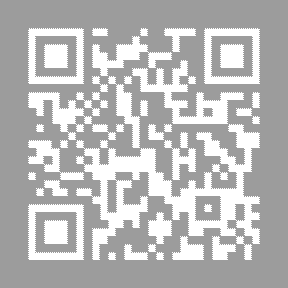 |
| パソコン甲子園2023の概要 | こちらを参照してください。 |

